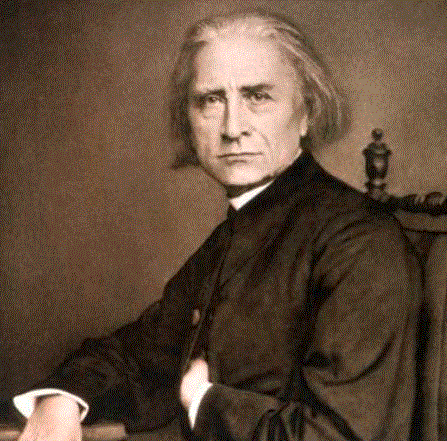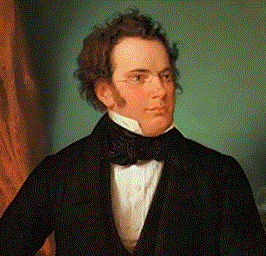Search Results
「」に対する検索結果が104件見つかりました
- 6/16/2022 音楽家と作品への雑感「ボロディン」
第8章 アレクサンドル・ボロディン Alexander P. Borodin (1833年~1887年、53歳没) グルジア系貴族の血を引いているロシア国民派の所謂「五人組」※の一人で、本職はペテルスブルグ医学大学教授で化学者.作風はディレッタント(dilettare 楽しませる・楽しむ)であり作品数は少ない.29歳で知り合ったバラキレフの国民音楽に対する情熱と理想に共感してから本格的に作曲に取り組む.しかし着手から完成までに年月が掛かり、36歳で作曲した「交響曲第1番」を好評裏に世に出した後、「交響曲第2番」※①は着手から完成まで8年を要している.36歳頃に書き始めた代表作の歌劇「イゴール公」※②は、スケッチのみの第3幕と第4幕を彼の死後にリムスキー・コルサコフとグラズノフがまとめ上げて完成した.「中央アジアの高原にて」※③はアレクサンドル2世即位25周年祝賀行事のために作曲され、「弦楽四重奏曲第2番」※④は1881年に作曲された. ※①「交響曲第2番」はロシア的な重さが無く、これがロシア国民派の音楽かと思わせる明るい親しみやすい旋律が多い.ロシア的旋律にアジア的旋律が加わった長閑(のどか)さがあり、チャイコフスキー「悲愴」などとは明らかに違うことに気づく.往年の名指揮者ワインガルトナー※は、ロシアの国民性を知るにはチャイコフスキー交響曲第6番「悲愴」とボロディン交響曲第2番を聴けば十分と言ったそうだ.日本では音楽愛好家の間で通称 “ボロ2”と呼ばれている. ※②「イーゴル公」より “ダッタン人の踊り” は一番よく演奏される曲だが、ポピュラー音楽界では Strangers in Paradise という曲名で、スタンダード曲、ミュージカルのナンバー等で同じくらいポピュラーな名曲. ※③交響詩「中央アジアの高原にて」はロシア皇帝アレキサンドル2世の即位25周年に際して作曲された.広大な中央アジアの草原の情景描写の中にオリエンタリズムが濃厚に聞こえる. ※④弦楽四重奏曲第2番ニ長調は細かい弦の動きが良く響く、時にボヘミア的な、又時にオリエンタルな優しい調べが続く美しい曲.第3楽章 “夜想曲 Nocturne” は独奏用にも編曲され有名. 直、ボロディンについては、その生い立ちと人間性及び作品 ≪弦楽四重奏曲第2番≫ に関して、編集者の見事な紹介(※下記のタイトル)があるのでそちらを参照して頂きたい. ※「ロシア5人組」アレクサンドル・ボロディンーString Quartet No.2 (2/27/2021) 今回の雑感記録に際して、改めて聴き直した作曲家の作品リストをご参考までに下記、表にした.
- 6/15/2022 音楽家と作品への雑感「スメタナ」
第7章 フリードリッヒ・スメタナ Friedrich Smetana (1824年~1884年 60歳没) チェコのパルドウビュッツ州(Litomyšl リトミッシェル)の酒造家に生まれ、単身プラハに出てピアノと作曲を学んだ.ボヘミア地方は当時、オーストリアの支配下にあり、チェコ独立革命運動が盛んで、スメタナも民族運動に加担して、義勇軍のための行進曲を書いたりしていたが、スエーデンのイエテボリに5年間難を逃れて指揮者を務めていた. 作品の中で「モルダウ」が特に有名で演奏される回数も多いが、これは連作交響詩「わが祖国」(全6曲)※①の第2曲目である.改めて全曲(演奏時間80分間)を聴き直してみると、「モルダウ」がエルベ川の上流にあたる大河の激流と小波を見事に表している名曲だと思う一方、他の5曲はチェコ民族の団結を意図して作曲されている感がして、闘争的な旋律や音響を感じる部分が多く、21世紀の現在のロシアによるウクライナ侵攻という理不尽な戦闘行為を目の当たりにしている時期でなく、平穏時に聴くと大変重苦しい感じがするだろうと思った. モルダウ川(Vltava ヴルタヴァ川)はチェコ北部に端を発し、ドイツ東部を流れ北海に注ぐ全長1091Kmの長い川.流域の主な都市はチェコのプラハ、ドイツのドレスデン、マグデグルグ、ハンブルグ.私はハンブルグに1960年代、70年代の2回に分けて5年間住んでいたので、エルベ川には色々な想い出があるだけに作品「モルダウ」を聴く度に思い出が蘇る. ※①連作交響詩「わが祖国」 1「ヴィシェフラド(Vyšehrad)」:プラハの丘の上の城の名前 2「ヴルタヴァ(Vltava)」(モルダウ(Die Moldau)):川の名前 3「シャールカ(Šárka)」:女戦士の名前 4「ボヘミヤの森と草原から(Aus Bo”hmens Hain und Flur)」:風景描写 5 「ターボル(Tábor)」:強く戦ったフス教徒の陣営の名前 6「ブラニーク(Blaník)」:砦のあった山の名前 ※②「ピアノ三重奏曲 ト短調」 各楽器の自己主張と調和とが程よく交差する民族的な旋律の曲. 今回の雑感記録に際して、改めて聴き直した作曲家の作品リストをご参考までに下記、表にした.
- 5/23/2022 ”The Avant” 高齢者施設訪問演奏
私が属するピアノ・トリオ・グループ、MONATS-Trioはパロアルトにあるリタイヤメント・ホーム”The Avant”で昨日、日曜日の午後(5月22日)に施設訪問演奏をした.初めの演奏は自立生活ができる居住者 (Independent Living) のホールで、次に擁護の必要な居住者のアシスティッド・リビング (Assisted Living) のホールでの二回の演奏.プログラムはピアソラの"Oblivion" (忘却)とメンデルスゾーンの"ピアノ三重奏曲op 66" で約一時間.The Avantは、正面玄関を入った直ぐのところにサロン兼ホールがあり、それぞれにグランドピアノが装備されている.約20〜25人の居住者が各ホールで私たちの演奏を鑑賞してくれた.車椅子の人もいれば、普通に歩ける人もいて、明らかに音楽を愛する方々で、たくさんの励ましの拍手を送ってくれた.私たちにとっては嬉しい聴衆であり、楽しく演奏できた演奏会であった. アーマチュア音楽愛好家、私たちについて _________________________________________________ 五十嵐恵美(ヴァイオリン) 東京で生まれ、7歳のときにヴァイオリンのレッスンを始める.10代の頃、東京で鷲見四郎氏に師事.現在アメリカと日本のアマチュア室内楽演奏家とアンサンブルを弾いて楽しんでいる.地元の弦楽器製作者であるローレンス・ハウスラー(2016年、カリフォルニア州パロアルト)に委託したバイオリンと、フランソワ・ル・ジョン(1775年、フランス、パリ)の2本のバイオリンを演奏している. Dr. ステファン・ルイッツ(チェロ) MONATS-Trio のロック(最も頼りになる存在)であるステファンはドイツで生まれ、ドイツ、フランス、米国各地で、大学のオーケストラ、様々な地元の室内楽グループで演奏してきた幅広い室内楽演奏経験の持ち主.現在、カリフォルニア州メンロ・パーク市に所在するSLAC National Accelerator Laboratory (Stanford Linear Accelerator Center)で働く物理学者. ノーマン・古田(ピアノ) 引退した弁護士であるノームは、南カリフォルニアで小学校時代にピアノを学び始め、Stanford大学法科に在学中に息抜きとして室内楽を演奏し始めた.40年後の引退により、ベイエリアの室内楽の友人と再び交流し演奏活動を再開. ノームの最新のこだわりは、4曲のブラームスの交響曲のピアノ三重奏用への編曲をみつけてヴァイオリン、チェロ、ピアノで演奏すること.
- 5/22/2022 音楽家と作品への雑感「ドボルザーク」
第6章 アントン・ドボルザーク Antonín Dvořák (1841年~1904年 62歳没) チェコのプラハ近郊のネラホゼヴィス (Nelahozeves, ドイツ語名 ミュールハウゼン, Mühlhausen) に生まれ、オルガン学校で学んだ後、チェコ国民歌劇場のビオラ奏者を務めながら、同劇場の指揮者であったスメタナからチェコ国民音楽の創造に強い影響を受けた. オーストリア政府奨学金を獲得した際に、その審査員であったブラームスの知遇を得て、作品が世に出るようになり、作風もブラームスの影響を強く受けている.アルト歌手アンナと結婚し、ビオラ奏者を止めて教会のオルガニストに就任.ブラームスはドボルザーク独自のスラブ様式を高く評価し、以後二人は終生変わらない友情で結ばれる.取り分け、ブラームスの推挙の出版社からの依頼で作曲した「スラブ舞曲第1集」(37歳時作曲)※① は彼の名を一躍有名にした.イギリスにも数回旅した順調な歩みの間に、長女を含む3人の幼児が相次ぎ死ぬという不幸に見舞われ、名作「スターバト・マーテル」※② は、この悲しみを聖母マリアに見出したカンタータである.プラハ音楽院教授にも就任し、米国のナショナル音楽院からの招きで渡米し、名曲「交響曲第9番 “新世界より“」※③ を作曲し、「弦楽四重奏曲 第12番 “アメリカ“」※④、「チェロ協奏曲」※⑤ と2年間で代表作品を次々と作曲している.他にも、「セレナード ホ長調」※⑥ も美しい. チェコの民族主義音楽はスメタナによって開拓され、ドボルザークによって国際的な広がりを見せた.スメタナが交響詩や歌劇で民族主義を打ち出したのに対して、ドボルザークはブラームスの影響が強く、積極的なチェコ民族音楽の響きは少なく、むしろ、郷愁の甘美さへの陶酔すら感じさせる. ※①「スラブ舞曲 第1集」(1878年作曲)の8曲はジムロック(Simrock)出版社からブラームスの「ハンガリー舞曲集」と同じ趣向の作品を依頼したことにより作曲.「スラブ舞曲 第2集」(1887年作曲)は第1集の成功により、その後に作曲された.民族音楽の面白さに加えて管弦楽曲として楽しめる. ※②「スターバト・マーテル」は、私が高校大学時代を通して所属していた混声合唱団倶楽部で1958年に東京のホールで全曲を歌った想い出のある曲で、改めて聴き直すと、穏やかな気持ちにさせられる大変な名曲である.「スターバト・マーテル」の作曲ではロッシーニ他の名曲もあるようなので、時間を見つけて是非一度は聴いてみたいと思う.⇒ 当時、混声合唱団で使用した楽譜. ※③交響曲第9番“新世界より“」は、ドボルザークの最後の交響曲で、特に演奏機会が多い名曲.アメリカの音楽院の校長として3年間ニューヨークで過ごした時の赴任直後に作曲された.アメリカ音楽の影響も多少感じられるが、アメリカからボヘミアへの郷愁を音で綴ったという印象の方が強い.直、「交響曲第8番」は“新世界より”に続き演奏機会が多い交響曲で、自然に音楽が流れ最もメロディーが多い名曲と言われているが、私は未だ聞く機会が少ないためか、今回の再聴では左程の共感を持てなかった. ※④「弦楽四重奏曲 第12番 “アメリカ“」は、“新世界より”と同じく、アメリカ滞在中にチェコ移民の住むアイオワ州の村で作曲された曲で、同郷の人達に囲まれ、随所に郷愁を誘う美しい旋律が満ちている私の大好きな名曲. ※⑤「チェロ協奏曲」もアメリカ滞在中の作曲で、超絶な技法のチェロと豪勢な響きの管弦楽が交響曲的に絡む作品で、古今のチェロ協奏曲中でも最高傑作の一つである. ※⑥「セレナード ホ長調」作品22は弦楽合奏からなる5楽章の作品だが、聴き心地のよい美しいメロディーが弦のみで奏でられる名曲である. 今回の雑感記録に際して、改めて聴き直した作曲家の作品リストをご参考までに下記、表にした.
- 5/6/2022 本のレビュー、レイティシア・ コロンバニ(Laetitia Colombani)著 三つ編み (La Tresse)
<あらすじ> 異なる国で、三人の女性がそれぞれの人生を送っている.インドでは、社会階層では生まれながらの不可触民であるスミタ.幼い娘には教育を受けさせたいという願いから、命からがら娘と町から逃亡する.イタリアでは、両親が経営する毛髪加工会社を手伝うジュリア.父の事故死がきっかけで、倒産寸前の会社をまかされてしまう.裕福な男性との結婚が解決策だと母は言うが、近くの海岸で出会った外国人に魅かれる.カナダではシングル・マザーの弁護士サラ.都会の法律事務所で女性初の管理職への昇進も目前だが、癌の告知を受ける.その事実を隠し続けるが、偶然知った同僚たちは態度を変え、昇進は今まで眼をかけていた後輩に行ってしまう.困難な状況に無我夢中で真っ向から取り組む女性達.物語は三人三様の人生が繰り広げられるが、結果として三人の運命は「髪」を通じて繋がっていく. <ブッククラブでの感想> 「最初の部分からの読みやすさと、また映画界出身の作者だけあって、行ったこともないインドの駅での光景や、ジュリアがイタリアでインド人男性と逢瀬を重ねる海辺などは、私の心の中にも映画の様に繰り広げられる映像があり不思議でした.三人の女性には、どれも違ったレベルでの苦悩があるけれど、各々の女性が自分自身の道を見出していく強さを感じました.」 「人間は自然に打開策を見つけて生きていくことを感じることが多く、この本はそれを象徴していたかのようでした.スミタの日常は生きるか死ぬか、中東で勃発している状況と似ていて読みながら切迫感がありました.ビル・ゲイツがインドのトイレや水道を改善するチャリティの話は知っていましたが、この本を読んだときには思い出せませんでした.スミタの家族が代々してきた手袋も使わないでするトイレ掃除の様なリスクの多い仕事が少なくなることを切に願います.これついて、男友達に話したら、この階層の人の職が無くなってしまい、さらにビル・ゲイツがしているインドのトイレや下水道改善のチャリティに意味がなくなるから良くない、という感想を聞き驚きました.ともあれ、この本によって気づかされることが多々ありましたが、「スミタが髪を売り、ジュリアがその髪を加工し、サラがその髪を化学治療の後で付ける」物語の最後の繋がりの部分は「あぁ!なるほど!」と思わせられ、暖かくポジティブなものを感じました. 「三か所の異国に住む三人の女性の話が最後に髪で繋がるとても素敵な物語でした.差別や伝統的価値観による悩みと勇気ある行動を上手に紡いでいて、映画を観ているよう.インドに住むスミタの環境が一番過酷ですが、三人が自分の環境から脱出するその勇気は同じで爽やかな読後感でした.」 「この本を読んだとき、ちょうど「Me Too運動」の最中でしたが、登場人物の女性達が戦う相手は男性ではなく、彼女たちが置かれた環境と状況だと感じました.」
- 5/5/2022 音楽家と作品への雑感「リスト」
第5章 フェレンツ・リスト Ferencz(Franz)List (1811年~1886年 74 歳没) リストは当時のオーストリア帝国領内のハンガリー王国の寒村ライディング(Raiding)で生まれた.父親はハンガリー貴族エステルハージ侯(Marquis Esterházy)の執事、母はドイツ人だった.両親が音楽に造詣が深かったことから自然にピアニスト及び作曲家としての道を進んだ.本人は生涯を通じてハンガリー人としての気概は高かったがハンガリー語は話せなかった.パリのサロン生活でフランス語に精通し、ショパン、ベルリオーズなどと知り合い、美貌の伯爵夫人マリー・ダグー(Comtesse Marie d'Agoult)と知り合い結婚し、娘コジマ(Cosima)~ 成人して、指揮者ハンス・フォン・ビューロー(Hans von Bülow )夫人、その後にワーグナー夫人となる ~ をもうける.後にドイツのワイマールに定住して、ドイツ語にも堪能でワイマールを嘗てのゲーテ、シラーの全盛期を偲ばせる隆盛に持って行った.晩年のリストは、その精力のほとんどをワーグナーの大きな理想であった「総合芸術」に向けて費やした.ロマン派音楽をワーグナーと共に派手に行動的に表現し、宗教音楽への精進を決意し聖職に入った晩年であった. 作曲では交響詩というジャンルを確立したが、改めてリストの作品を聴き直すと超技巧ピアノ曲が数多く、演奏家にとっては演奏が至難の技であろうと改めて思った.兎に角、的確な表現ではないかも知れないが、後のワーグナーに近い作風であり、難解な作曲家ではある. 以前、あるピアノ講師から聞いた話ではリストの作品を演奏するには、手の指を強化する必要性は許より、手の指が大きいか、差ほど大きくなくても指が十二分に開かないととても演奏できないそうだ. 「パガニーニ大練習曲(全6曲)」の第3番 ≪La Campanella≫ は特に有名で、他にも「愛の夢」や「ハンガリー狂詩曲(全19曲)」の第2番や「ピアノ協奏曲第1番」が耳馴染みのあるメロディーである.しかしリストの作品は「超技巧練習曲」と銘打った曲を始め、それ以外でも本当に息つく暇もないようなリズム、テンポ、メロディーの曲が多くポリーニ (Pollini)、ポレット (Polet)、キーシン (Kissin)などの名手で聴くことが出来る今日の時代に聴くとこができ良かったとつくづく思う. 1曲だけの「ピアノソナタ ロ短調」は40歳代の作曲で、シューマンがリストに贈った「ハ長調幻想曲」に対する返礼として、リストがシューマンに献呈された作品であるが、演奏時間30分が単一楽章で構成されている.初演は音楽教師としてのリストの高弟(門下生)であるハンス・フォン・ビューローにて行われ賛否両論あったが、今日ではピアノソナタの傑作の一つと評価されている.ピアノソナタと言っても“ドラマティックな展開の華麗な曲想“でピアノによる幻想曲か交響詩と言っても良い. リストは交響詩という音楽構成の生みの親であるが、交響詩「前奏曲」と交響詩「マゼッパ」を改めて聴き直した.リストの一つのパターンである暗黒から光明~闘争~憩い~勝利といったプロセスで曲は構成されていて、大方は激しく時に静かに演奏されて行く. 「スペイン狂詩曲」には、この旋律の中にアメリカ映画のアラモの砦のメキシコ軍との攻防を描いた話題作「アラモ」(監督・主演ジョン・ウエイン)のテーマ曲と非常に似た旋律が出てくることを、私は10数年前にピアニストの演奏会で気づいている. 今回の雑感記録に際して、改めて聴き直した作曲家の作品リストをご参考までに下記、表にした.
- 4/15/2022 私の最愛なるジェット(from North Carolina)
私の春のプロジェクト、庭作り、を助けてくれる私の最愛なるジェットは、人懐こい生後14か月のシェパード犬で、私が苗床の上にシートを敷くのを助けてくれているつもりです.ジェットはいつも私が取り組んでいるものの上に立ってボールを落としているので、私のプロジェクトは結局あまりかたづきません. ジェットは私の後を常に付きまとっています. 服従のためには最高ですが.、ホームプロジェクトの完了には最悪です😊 ジェット、草刈り手伝う ジェット、とても幸せ ジェット、グレンデルと綱引き
- 4/12/2022 音楽家と作品への雑感 「シューベルト」
第4章 フランツ・ペーター・シューベルト Franz Peter Schubert (1797年~1828年 31歳没) 第4章にシューベルトを選んだ理由は何故か? 一昨年 (2020年) はベートーベン生誕250周年記念の年、昨年 (2021年) は5年振りのショパン国際コンクールの年で、それぞれの年に対象の作曲家の作品を演奏するコンサートやテレビ放送が非常に多く、少々聴き飽きた一方、シューベルト作品を聴く機会が少なかったので、じっくりと聴きたいと思った次第. ウイーン近郊のリヒテンタール (Lichtental) に生まれたシューベルトは、農民出の教師の父親の最初の妻との間の14人の子供の第4子だった. 幼い頃に父や兄から楽器の手ほどきをうけ楽才を発揮していたが、12歳で王立礼拝堂の児童合唱団員として神学校コンヴィクト (Konvikt) に入学. 初等から高等学校までの課程を修了すると共に音楽の専門教育を授けられた. 16歳でコンヴィクトを去り、父親の手助けをし師範学校に通いながら作曲活動を始めたが、楽器演奏は左程の才能が無かったようで、音楽教師をしながら弟子たちからの支援で生計を立てていた. 生地リヒテンタールの教会で初演した 「ミサ・ヘ短調」 のソプラノ歌手、テエレーゼ・グローヴ (Therese Grob) 、に想いを募らせたが彼の内気な性格で実らなかったが、その後、19歳頃から作曲した「交響曲第4番」「第5番」や「鱒」「死と乙女」などでは、既にシューベルトの歌曲作曲家としての作風の充実と完成を見せている. 20歳の頃、以前から世話になっていた詩人の F.ショーバー (F. Showbar) の紹介で知り合った20歳年上のバリトン歌手、ヨハン・フォーグル (Johann Vogel)、 と無二の親友になり、シューベルトのリード(歌曲)が彼の公開演奏で好評を博し、良き友人の助力で彼の名声は次第に高まり、シューベルトを中心とした友人たちの集まり「シューベルティアーデ」 (Schubertiade) が結成された. 20歳代後半に「美しき水車小屋の娘」「冬の旅」や「交響曲第7番《未完成》」等を次々と作曲し、30歳の時に尊敬していた同じウイーンの大作曲家ベートーベンが3月に没し、彼も松明を持って葬列に参加している. その年の9月にはグラーツ (Graz)を訪れ自作の演奏会を開いて快適な日々を送り、「即興曲」「楽興の時」など作曲した. その翌年3月の自作発表会で大成功を収め、初めて大金を手にした彼は借金を返済し、友人にご馳走し、念願の新しいピアノを買って大金を使い果たした. その年の10月にハイドンの墓参に出かける旅立ちをした. その後は健康が急激に悪化し11月にチフスと診断され生涯を閉じた. 本人のうわ言を尊重して遺骸は尊敬するベートーベンの墓の近くに埋葬された. 交響曲第8番 「ザ・グレート」 は聴きとおすのが大変な長さだと、学生時代にレコード観賞会で講師が紹介していたことを時々思い出すが、私の今の年頃には丁度良い長さに思えて、心が休まる旋律が流れる大変な名曲と感じる. 聴きなれたカール・ベーム指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏を聴くと私は特に落ち着く. 又、デーヴィット・ジンマン指揮NHK交響楽団 (2009年) 演奏も大変に楽しめる. 交響曲第7番「未完成」も劣らぬ名曲だが、副題が 「未完成」 と言うだけあって、もう少し長く聴きたいと思うのは勝手な贅沢かも知れない. 交響曲第2番はモーツアルト的だが第4番 「悲劇的」 になるとベートーベン的な弦の重厚な響きが随所に聴こえる. ピアノ曲 「楽興の時」 は歌曲を彷彿させる美しい旋律が随所に表れ、特に第3番(ヘ短調) はNHKの音楽番組のオープニングにも使われてから一般にも愛好されている. ピアノ五重奏曲 「鱒」 は眞に名曲. ヤン・パネンカ (ピアノ) とスメタナ四重奏団の録音は聴く度に魂を揺さぶられるほどの名演奏、名録音だと感じる. ピアノ三重奏曲第2番は長調ながら悲しげな短調的旋律が随所に流れシューベルトらしい名曲だと思う. 最後のピアノソナタ第21番は眞に神聖な天上の音楽と言うにふさわしい至高の傑作である. 歌曲集 「美しき水車小屋の娘」 は歌唱力のあるディートリッヒ・フィッシャーディスカウの演奏で、ごつごつしたドイツ語の発音を緩急の曲がほぼ順番に並べられた美しい歌曲を全曲通して聴くことができる. 歌曲集 「冬の旅」 はハンス・ホッターの歌で全曲をこれまで数度聴いたが 「おやすみ」「菩提樹」「春の夢」 以外は暗い曲であまり好きになれないのが正直なところ. ずうっと現代に近いクリスティアン・ゲルハーヘル (バリトン) とゲロルト・フーバー (ピアノ) の全曲を聴いたが、こちらは遥かに聴きやすく歌詞が説得力ある内容として伝わってきた. 作曲家の死の1年前に書かれた曲で、死に対する不安、恐怖、絶望などが表現されているのか. かのアインシュタインによると、シューベルトが偉大な作曲家になったのは、連弾曲が友情の証だから…とか、ピアノ連弾にも佳作が多い. シューベルトの曲は簡潔な中に高い芸術性がある気がする. シューベルト曰く、「私が愛を歌う時、それは苦悩となる. 私が苦悩を歌う時、それは愛となる」. 眞に、至言であると思う. 今回の雑感記録に際して、改めて聴き直した作曲家の作品リストをご参考までに下記、表にした.
- 2/28/2022 MONATS-Trio Concert on Saturday, February 26, ― アマチュアの楽しみ
新しいピアニストのメンバーが昨年の夏から加わり、コロナ禍の中、2月26日土曜日の午後、2年ぶりに近所の教会でのコンサートを無事終えた.カリフォルニア州、および、サンマテオ郡では2月16日よりマスク着用の規制が取れたため、幸運にもマスクなしで演奏ができたが、各々当日の朝、COVID-19のテストをしてNegativeであることを確認してからの演奏であった.家族、友人の暖かいサポートを受け、現在まだまだ演劇、コンサート等への外出を控えている人が多いなか、約30名弱の方々に来ていただき (演奏に反省はあったとしても)アマチュアの演奏としては精いっぱいの演奏であった.そして以外にもたくさんのお褒めのお言葉をいただいたことは嬉しい限りであった. プログラムは、 Oblivion Astor Piazzolla (1921-1992) Arr. for violin, cello, and piano by José Bragato (1915 - 2017) Piano Trio in G major, Hob, XV: 25 “Gypsy” Joseph Haydn (1732 - 1809) · Andante · Poco Adagio · Finale. Rondo all’Ongarese. Presto Piano Trio in C minor, Op. 66 Felix Mendelssohn (1809 - 1847) · Allegro energico e con fuoco · Andante espressivo · Scherzo. Molto allegro, quasi presto · Finale. Allegro appassionato アマチュアの楽しみとは(アンサンブルの場合)勿論音楽好きで、ともに演奏することが至上の楽しみ、また喜びであって、その成果を家族友人と分け合いたいと思う、大変に「ソーシャルな楽しみ」であることを最近特に感じるようになった.勿論向上心は常にあってもプロとの違いは皆自覚しており、結果はさておき「弾いて楽しむ」」ことが第一の目的であることは、MONATS-Trioの共有している価値観であり、メンバー間の競争はなく、気が合う仲間という大変に居心地の良い趣味の世界である.
- 1/18/2022 楽器演奏とキネマの会の道半ば ~退職後に始めた趣味の世界~(part 1 of 2)
サックスとの出会い 約20年前にビジネスマンとしての会社生活を終える頃から楽器(サックス)演奏を始め、暫くして仲間を募って演奏グループとして「宝塚マスターズ・アンサンブル(愛称:TMA)」を立ち上げ、主として高齢者施設でのボランティアで当初は月に1~2回演奏しました.同じ時期に映画と音楽を楽しむ会として「宝塚キネマと音楽を楽しむ会」(通称:キネマの会)をほぼ毎月開催し、こちらはこれまでに220回を重ね、合計350本程度の名画の鑑賞と、時にはゲスト演奏者を招いての演奏を楽しむ会を続けてきました. サックスとの出会いは20数年前に楽器教室での体験レッスンを始めた時からで、生来の音楽好きであったとはいえ、特別にサックスが好きだったわけではありません.しかし奇妙な事に、1961年に当時は大手の繊維会社に就職して初めて赴任した大阪府南部の工場で、6カ月の経理実習をしていた間、女子バレーボール・チームのマネジャー(実際はボール拾いや声掛けと対外遠征試合の同行)を課長から命ぜられてやっていました.6か月後に兵庫県の工場へ転勤するのですが、その際にバレーボール・チームから餞別にもらった物が、何とジャズ・サックス奏者の大御所ソニー・ロリンズ演奏の1枚のレコードでした. それから数十年後に私がサックスを吹き始めた頃に、ずぶの素人女子高校生たちが吹奏楽を始めて全国優勝まで上り詰めるという痛快な映画「スイング・ガールズ」が大ヒットしました.この映画のモデルとなった高校は諸説ありましたが、その内の一つ長野県のある高校の指導部の先生にアポを取り、同校を訪問し映画撮影までの秘話をお聞きました. 当時のレコードジャケット⇒ 訪問した長野県のある高校の映画「スイングガールズ」関連展示物 「映画・ミュージカル・楽器演奏 ~感動が生き方を変える~」ミニ演奏会開催 思い起こせば、2006年に「映画・ミュージカル・楽器演奏 ~感動が生き方を変える~」というタイトルで、現在の自宅のある兵庫県宝塚市の「ソリオ・ホール」で市民を対象に全4回の講演とミニ演奏の会を開催したのが、その後の私の活動の端緒であったと思います. 元来音楽好きだった私はサックスに出会ってからは、勿論上手に吹きたいとは思っていましたが、それよりも好きな曲をどんどん吹きたいという思いが先に立ち、映画音楽、ミュージカル、クラシック、スタンダード、カンツオ―ネ、ジャズっぽい曲、演歌、童謡などレパートリーは急増しました.近年は楽譜はあまり出回ってない往年の名画の音楽(例えば「パリの屋根の下」「めぐり逢い」など)を、講師の先生にCDを聴いて頂き、音符を起こして頂いて(いわゆる採譜)サックスで吹くといった方法でも曲数はより増えました. サックスは19世紀中ごろにベルギーのアドルフ・サックス氏が発明した楽器で、2014年がアドルフ・サックス生誕200年に当たり、世界各地でイベントが開催されました.私は運よくその年にオランダとベルギーに2週間家族旅行で行く機会があり、アドルフの生誕地ベルギーのディナン(Dinant)市まで足を延ばし、ムーズ川に架かる長い橋の全欄干にカラフルな楽器サックスを飾り付けているという、極めて特異な景色を見る事も出来ました. ムーズ川に架かる長い橋の欄干(ディナン市) アドルフ・サックス・ミュージアム前 「宝塚マスターズ・アンサンブル」などでサックスを吹く場所は高齢者施設でのボランティア演奏が中心ですが、他に演奏した思い出の場所では、「宝塚文化創造館(旧宝塚音楽学校校舎)」のオープニング、兵庫県篠山市のビレッジ、宝塚西谷の森公園、奈良市、大和郡山市、守口市、枚方市、西宮浜、吹田市千里、大阪市の堂島、梅田ハービスENT、天満橋、新大阪や横浜市港北区日吉、東京都港区三田、N.Y.州のシラキュース市、ミズリー州セントルイス市などで、さすがに最近は宝塚市内が活動の主たる場所に落ち着きました. 結成当時のTMAメンバー ピアノとサックスの二重奏風景 オープン当時の「宝塚文化創造館」 「宝塚キネマと音楽を楽しむ会」 「宝塚キネマと音楽を楽しむ会」は、当初は会場として宝塚市内の2つの公民館を使って映画の上映やゲスト演奏者の演奏をしていましたが、映画上映のための機材(プロジェクター、DVDプレーヤー、音声再生機、コード類他)を自宅から大型の旅行用スーツケースに入れて、電車を乗り継いで運び、現場で組み立て、終了後に片づけて自宅へ戻す迄の作業と更に公民館の部屋取りも行い、その上に上映作品の選定と来場者へのプログラム作成など、相当に好きでもなければ出来ないことをやってきました.数年前から会場を自宅マンションの「集会室」を借りることに変更したので時間的な負担は半減しました.映画上映や演奏が終わると会員同士の親睦を目的に公民館の日本間や居酒屋で乾杯をするのも楽しみで、また春秋には自宅近くの山小屋風の宿を借りて、映画及び音楽仲間と美味な神戸牛でのすき焼きパーティを開いてきました. 「宝塚キネマと音楽を楽しむ会」の仲間たち 山小屋風の宿でのランチ・パーティー風景 筆者後記: 本稿は5~6年前に以前に勤めていた企業のOB会の季刊誌に投稿した文章を現在の自己の状態に照らして一部表現を改めたもので、修正しても直、冗長な表現であったり、分かりにくい部分が多いと思いますが、オリジナリティを損なわない程度に留めたので、その点をご理解いただきたくお願いする次第です.’Part2’ 私の「クラシック映画論」も宜しければご笑読ください.
- 1/18/2022 楽器演奏とキネマの会の道半ば ~ 私の「クラシック映画論」~ (part 2 of 2)
私の「クラシック映画論」 昔の映画は名作・佳作が多いと思いますすが、世代が変わると説明しても中々に伝わり難いのが常で、数年前から私が思う「クラシック映画論」について、以下のように説明すれば他の人に分かりやすいかな~と思うようになりました. 現代は兎にかく毎日が忙しい!!! IT(またはコンピューター)が発達し、情報はスマホやラインで見たりやり取りする社会がその傾向を一層助長しているように思えます. 私の生きてきた時代も高度経済成長期であり、大変忙しかったように思いますが、ITがまだ未開発の時代だったので情報を瞬時に取得することは難しく、情報のある所や場所へ出向く(アクセスする)必要がありました.つまり、辞書や百科事典を紐解いたり、新聞や雑誌を見たり、映画を見たり、音楽会を聞きに行ったり、レコードを聴いたり、絵画展に行ったり、読書をしたり... この中で前半部分、すなわち辞書や百科事典を紐解いたり、新聞や雑誌を見たりが、ITの発達のおかげであまり必要とされなくなりました.そして後半部分、つまり映画を見たり音楽会に行ったり、レコードを聴いたり絵画展に行ったり、読書をしたりは、映画を見たり以外は、音楽、図工、国語といった小中学校で知育として学ぶ授業の課目にある分野であり、好きか嫌いかは個々人で違うにしても、基礎的な知識と実技は学ぶ機会のある芸術文化であることが分かります. 音楽についてはクラシック音楽の歴史について、バッハ、ヘンデル、ハイドン、ベートーベン、モーツアルト、ブラームス、ショパン、メンデルスゾーン、チャイコフスキーやドビュッシー、ラベル、ビゼー、ムソルグスキーなどから近代のヒンデミット、ベルグや武満 徹まで名前は教科書にも出てくるし、ピアノやオルガンを伴奏に歌を唄い合唱するという授業もあります.絵画も図工の時間に、画家の歴史について、ボッティチェリー、ミケランジェロ、ラファエロ、ミレー、コロー、レンブラント、モネー、ルノアール、ドガ、ターナー、ピカソ、ゴッホ、クリムトなどの名前と代表作が教科書に印刷されていたし、西洋文学ではシェークスピア、ヘルマン・ヘッセ、トルストイ、ドストエフスキー、ヘミングウエイ、日本文学では森鴎外、樋口一葉、夏目漱石、山本有三などを必ず思い出します. 映画は娯楽か芸術か「クラシック映画論」 映画を芸術文化と認めるか否か、つまり単なる娯楽か大衆芸能と考えるかどうか議論の分かれる所かと思いますが、学校の授業では取り上げられないこともあり、また一本の作品を鑑賞するには最低でも2時間程度は時間を必要とします.又どれが良い作品なのか分からないし、私の思う良い作品は殆どが1940年代、50年代、60年代に集中していて、それらの作品を見る機会はなかなかない.感動を呼ぶ良い作品(傑作とか秀作)に行きつかないのが現代の社会ではないかと思います.傑作・秀作と呼ばれる映画は、原作や脚本及びテーマがしっかりしているものが多く、それを支える監督、俳優、キャメラ、音楽がまたしっかりしているためだと思います. 1970年代以降に制作された映画は、強い刺激を求める人たちには満足のいく作品かも知れませんが、観る人に感動を与える良い作品は極めて少ないと言っても過言ではありません. 依って、現代の人たちが少ない時間を割いて劇場で見る映画は、例えば文学で言えば古典を読むことなく、いきなり村上春樹やカフカを読んだり、絵画で言えば印象派の絵画を鑑賞することなく、いきなりピカソや池田満寿夫の作品を見ていたり、音楽で言えば古典派やロマン派の名曲を聴かずして、ベルグや武満 徹の音楽に接している可能性が高いと思います.どんな芸術文化でも同じですが、良い作品に出合うまでには、その数倍又は時として数十倍もの平凡な作品や駄作、見るに値しないくだらない作品を見聞きする中から、良し悪し (好き嫌いも含めて) の価値基準が自ずと自分の中に出来てくるもので、その過程もまた大切だと思います.しかし、現代社会はあまりにも忙しいのと、映画に関してはもう一つ厄介なことに、作品の保存状態で経年劣化してカラー物は色彩が衰える度合いが、他の芸術文化の作品に比べかなり激しいので、古い時代の映画を沢山見ることは、殆ど不可能に近いと思います.音楽ではレコードが同じように劣化しますが、音楽の場合には作曲家の作品の演奏であり、演奏者の作品の劣化であって、映画のオリジナリティとは少し異なると思います.私の思う感動をもらう良い作品(傑作や秀作)は、1960年代以前に殆ど制作されていて、従って、それらの事を私は「クラシック映画論」という呼び名で理解して頂こうと思うようになりました. 筆者後記: 本稿は5~6年前に以前に勤めていた企業のOB会の季刊誌に投稿した文章を現在の自己の状態に照らして一部表現を改めたもので、修正しても直、冗長な表現であったり、分かりにくい部分が多いと思いますが、オリジナリティを損なわない程度に留めたので、その点をご理解いただきたくお願いする次第です. ’Part 1退職後に始めた趣味の世界’ も宜しければご笑読ください.
.png)