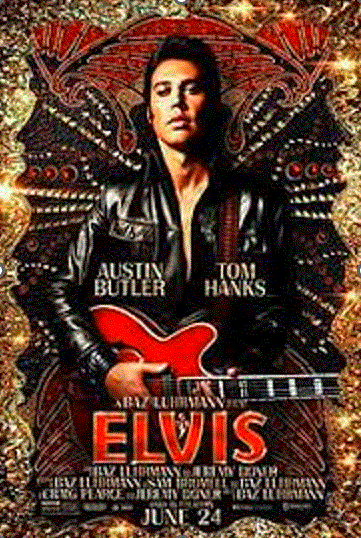Search Results
「」に対する検索結果が104件見つかりました
- 1/12/2023 体力の衰えについて、1月4日編集者のブロッグへのコメント
体力の衰えについて (1月4日編集者のブロッグ) 私がジムで言われたのは、一日一度は汗をかかなければCardioのエクササイズに欠いてしまい体力も筋力も衰えると. 家の中でスクワットと膝をついて腕立て伏せを50回ずつ、そしてロシアン・ツイストを100回、これだけでも汗が出ますので、運動できない日は寝る前にこれをしています. 外を歩く時は早歩きでこれも汗がでるくらい、だそうです. ご参考まで.
- 1/9/2023 最近の日本、1月4日編集者のブロッグへのコメント
3年間のブランク後の日本の印象は大変参考になります (1月4日編集者のブロッグ). 略、私も同じような感覚で毎日を生活しています.物価高、少子化、技術開発力及び生産力の沈下が進むこの日本をどのように再興するか.道筋を全く示せずに政治はその日暮らしで進んでいる感じがします. 食料自給率の低下と本質的な低さ、エネルギーの外部依存、自然災害の多さと災害規模の順次拡大、どれをとっても根本的に30年~50年単位で、それこそ骨太の方針を立てて掛からないと解決できない問題ばかりです. インフレは何が主な原因かを政治家は考えていない可能性が高いです.今回の日本のインフレはロシアのウクライナ侵攻より少し前から始まっており、その後に急速な円安が進んでいるので、分析すれば、略、因果関係は明示できると私は思っています.それなしに、賃上げをインフレ率以上に挙げよと政府が言っている事自体は極めて奇妙で無責任です.インフレが今後どうなるかを予測せずに賃上げを続けられる企業は極ごく一部の大企業だけの筈ですが・・・.
- 1/9/2023 反田恭平の音楽観と行動力
最近の音楽番組を垣間見ているとピニスト反田恭平(28歳)※(注)の活動の着眼点の良さ、活動範囲の広さに特別の興味を惹かれることが多い. 反田恭平氏は言わずもがな、一昨年(2021年)第18回ショパン・コンクールで第2位を獲得したショパン・ピアニストであり、それだけでも彼の演奏会は日本及び世界各地でびっしりと組まれている筈だと思う. しかし、最近テレビで目にする彼の活動範囲は、私の想像を超えて広く、深く、それらを何気なく自然体でやっているように見えるところに凄く惹かれる. 恒例のウイーンフィル・ニューイヤー・コンサートでは会場の ウィーン楽友協会大ホール(Wiener Musikverein)で、リハーサルから本番まで聴衆として聴く一方で、NHKのLIVE放送のコメンテーターとして会場と特別室を行き来していた.同氏は元々、音楽を指揮者の立場で考えることに興味があることを、色々な場で発言しているので納得できる.この放映ではウィーンの同氏の自宅がちょっと紹介された. ウィーン同様、同氏が奈良県に活動の場を広げているのは以前から知られていたが、先日の「題名のない音楽会」で彼の奈良での活動の一端が紹介され興味が沸いた.ホルンという楽器がヨーロッパ中世の貴族が鹿狩りに使う楽器だったことは知っていたが、同氏はホルンを奈良公園の鹿寄せに使うことを考えて実施してみたら、見事に鹿の群れが集まって来た情景が映されていた.更に、老舗の奈良ホテルには大正11年(1922年)にアインシュタインが弾いたピアノがあることは以前から知られているが、このピアノを使って同氏がショパンを演奏したことも番組で披露された. どちらも、目新しいことではないが、実際にこれまで誰も行動に移してこなかったことを、同氏は外連味なくさっさとやってしまう着眼点の良さと行動力に、私は特別の新鮮さを感じる. 奈良県はその歴史的価値の高さの割に、京都に比べて交通の便や道路の狭さ、宿泊施設の少なさ等で観光客数が京都より少ないことが言われている.しかし、同氏のような取り組みは奈良県の持つ本来の魅力を外部に発信するには大変に良い企画・発想であると私は思う. (1900 年頃製作されたニューヨーク・ハリントン社製アップライトピアノ) 直、同氏はJapan National Orchestra株式会社(以下、JNO)を設立している.工作機械大手のDMG森精機株式会社の出資により設立され、国内外で助成・支援活動を行っている一般財団法人森記念製造技術研究財団と、自らが代表を務める株式会社 NEXUSの出資により実現.代表は反田氏とDMG森精機 専務執行役員の川島昭彦氏が務め、反田氏とJNO所属のソリスト17名で構成される.JNOは、DMG森精機の創業地・奈良を本拠地に、持続的で発展的な音楽活動を行い、将来的にはアカデミーの創設も目指しているという. 現在の日本には将来を嘱望される若手音楽家が多く見られるが、その中でも反田恭平氏はその着眼点、活動範囲の広さ、実行力では驚くほどの動きをしているので、特に注目して行きたいと思っている. ※(注)反田恭平プロフィール:北海道札幌市生まれ東京育ち.桐朋学園大学からモスクワ音楽院に進み、第18回ショパン国際コンクール第2位.小林愛実(27歳、第18回ショパン国際コンクール第4位)と今年(2023年1月1日)に結婚している. 昨年(2022年)11月に私は小林愛実ピアノリサイタル(@いずみホール大阪)を聴きに行った.
- 1/4/2023 第8波コロナ禍の中での帰国 ― 雑考
丸3年ぶりの帰国.シリコンバレーにおける感謝祭、クリスマス休暇前後の雑踏、交通渋滞、殺気立った人の気配を避け、第8波コロナ禍の中、心配ではあったけれど思い切って帰国した.月一でヘルパーさんに通空通水はお願いしていてもやはり3年間住人のいないマンションに起こる予測できない水回りに関する事故の心配もあり、このタイミングでの帰国は結果的には正解だった.給湯器もこの折に新しいものに変えた.この品薄の時期に東京ガスのサービスには脱帽.また今回は日本アマゾンの宅配サービスも大変に重宝だった. Zoom等の便利なコミュニケーション・ツールは多々あれど、face-to-faceのコミュニケーションは段違いに効果的である.ましてやアンサンブルを弾くとなるとその効果は拡大.今回の帰国は母の13回忌が本来の目的ではあっても、アンサンブルの練習、友人、従妹、家族との観劇、歓談、会食と忙しくも楽しい6週間であった.但し、今回特に感じたことは3年間米国内にとどまり遠距離の旅行を控えていたこともあってか体力の落ちには驚愕した.コロナ禍以前は時差にしても、長旅の疲れにしてももっと早く調整ができたのに今回はいつまでたっても時差ボケ、旅の疲れが残っていた.3歳としをとったことにも起因しているとしても体力維持は2023年の課題だと思っている. 今回、大変に嬉しかったのはアンサンブルの仲間が増えたことである.(東京都)中央線近辺の住人からなるAPAのメンバーが主だが、新しくチェリスト(経験豊かで非常にお上手なプレーヤー)とフルーティストと練習する機会を持て、2023年4月の国際音楽祭において新しいプレーヤーとアンサンブルができることが今から楽しみだ. 米国においては2022年2月のコンサートで一緒に弾いたNormが腱鞘炎で続けることが無理となり非常に落胆していたところ、幸いにも米国のAPAのメンバーのピアニスト(若いピアニスト、Andrew)とこの1月半ばからメンデルスゾーンのピアノ・トリオ(OP49)の練習を始められることになった. 滞在中見聞した日本の現況は恐らく世界のそれと良く似たものだと思う.まず、防衛防衛費拡大増額、原発再稼働、物価高、不況、失業率の増加、貧困層の拡大、統一教会問題、等々の問題が山ずみの中で国民の政治・政治家不信は顕著である.少子老齢化、コロナ禍で顕著となった教育問題、なども全く方向性が決まらない中、ある意味で国民の怒りと諦め、或いは方向性が見えないための混乱もあるようで世相はあまりよくない.日本経済の見通しもつかない中、メディアではアンチ・エスタブリッシュメントとしてなんといった方向性も示さず単に屁理屈を述べる評論家が多いように見受けられた. 戦後78年が過ぎ、現在日本は政治、経済、社会、またそれに伴う基本的な価値観の変換の過渡期にいる.様々な問題を抱えている社会ではあるが(最近やや変わってきたとはいえ)日本は安全で、清潔で、食事が美味しく、知的レベルも高く、マナーの良い ”パラダイス” だと思う.日本国民の ”民度” が高いという意見をよく聞くが、今後その民度の高さを保持して、長期的に(独自に)発展していける国の舵取りは難題で楽観的には語れないと思った.読者の皆さまのご意見を伺いたい.本年も変わらずよろしくお願いします. 1/9/2023 コメント 飯田武昭 1/12/2023コメント Yuki T.
- 10/31/2022 フィルム・レビュー "ター" TÁR
ドラマ・音楽 レーティング: R言語と短いヌードの描写 出演: ケイト・ブランシェット, ニーナ・ホス, ノエミ・メルラン, ソフィー・カウアー 監督:トッド・フィールド 脚本:トッド・フィールド クラシック音楽の国際的な世界を舞台にしたこの映画は、現存の最も天才的能力を持った偉大な作曲家兼指揮者の ひとりと考えられているリディア・ ターを中心に描いている.クラシック音楽の世界では非常に珍しいことではあるが、彼女は女性で初めてベルリン交響楽団の首席指揮者になる.優秀な作曲家兼指揮者、この組み合わせが、リディアに 権力、POWER を与える. 半面、リディアの非常に敏感な聴覚は、しばしば彼女の気を散らし、様々な形で雑音として彼女の日常生活をおびやかす.ドアベル、メトロノーム、女性の叫び声、水が滴る音、等々は彼女を圧倒し、最終的には彼女を破壊的で感情的な道に導く. 私はクラシック音楽が大好きだが、楽器を演奏することも、楽譜を読むこともできない.クラシック音楽の訓練を受けたミュージシャンであることがどのように感じられるかについて、私には何も解らない.しかし、この映画は私にとって非常に啓発的であった.クラシック音楽の芸術が他のビジネスと同等に(あるいはそれ以上に)競争的で政治的であるとは考えもしなかった.この映画は、音楽についてよりもそれにまつわるPOWER、権力についての映画だと思う.権力は善にも悪にも使える.営利目的か芸術目的かは問わない.権力は、武器にも道具にもなり得る信じられないほどの”力“である. この映画は理解するのが難しい場面がたくさんでてくる.強烈、また残忍でもあり、時に意味が不明瞭な場面もある.それらは狂人ともおもわれる芸術家から発せられるものであり、理性的な心の状態の常人には理解しがたいものなのかもしれない.この映画は、強者と弱者の戦いでもあり、だれが権力を持ち、その権力者がどのようにその権力を使うかについて、強力な声明を出しているのではないかと思う. ケイト・ブランシェットは私の大好きな女優の ひとりである.この映画は彼女がこれまでに演じた中で最高のパフォーマンスの ひとつだと思う.この映画では、ブランシェットは彼女の創造性の頂点にいる.少なくとも、この映画を観て、キャリアの頂点に立つ女性を目の当たりにすることは価値があると思う.映画の早い段階で、彼女のキャラクターであるリディアがジュリアードでクラスを教えているシーンがある.それは激しく、残忍で、難しい対話に満ちてる.この5分間のシーンをブランシェットはノンストップ、ノーカットで演じる.改めて彼女は素晴らしい女優だと感じた. トレーラー: https://www.youtube.com/watch?v=Na6gA1RehsU https://www.cinemacafe.net/movies/33627/
- 9/26/2022 物語のある風景 ~(コロナ禍に開催された洋画家の個展)
昨年8月に紹介した洋画家の個展が大阪市の阪急百貨店うめだ本店で、先日(2022年9月)2年ぶりに開催されました。初日と知人、友人を案内して他にも複数回訪れました. 今回の展示は“物語のある風景“というテーマで、絵の中に可愛いクマやネコが登場する絵も含め約40点が展示されました. 本人によると、現在の画風は小学生の頃、自宅の玄関に飾ってあったアメリカ人の風景画家ロバート・ウッド(Robert Wood)の画風に憧れて描き始めた風景画とのことですが、私が思うに、既にロバート・ウッドから発展し幻想的風景を加味した神秘的な側面が加わっているように思え、一般の人気も増しているようです. この個展に先立つこと約2ヵ月前に、この画家の所属する日洋会の展示会「日洋展」が兵庫県の宝塚市文化芸術センターで開催されました。こちらは各画家の出展作1点ずつが全て略100号という大きな物ばかりで、それなりの迫力が感じられる作品ばかりでした. コロナ禍に開催された「日洋展」に出展のこの画家の絵 “おだやかな日々を想う時“ その画家の名前は有賀麻里さんと言います.
- 9/25/2022 音楽家と作品への雑感 「ヘンデル」
第9章 フリードリッヒ・ゲオルク・ヘンデル Georg Friedrich Händel (1685年~1759年 74歳没) ドイツのハレにJ.S.バッハと同年に生まれ、ハレ大学で法律を学んだ後、当時歌劇の盛んだったハンブルグに出た.その後、イタリアで活躍後にハノーバー選帝侯の宮廷楽長になったが、間もなくロンドンに出て歌劇を上演しロンドン市民権も得て、生涯ロンドンで活躍することになる.バッハが教会音楽家だったのと対照的に、ヘンデルは劇場又は公開演奏用の作品を中心としていて、ドラマティックで色彩的な要素が強く、特に合唱曲に優れている. ヘンデルの作品を生で聴く機会は、自分の70年位前の若い頃に比べて近年は格段に少なくなっていると改めて感じた.この間にジャズ、ロック、ポップス、ラップなど若者が好む音楽が巷に溢れ、他方でクラシック音楽の生演奏を聴く機会は当時より増えたものの、マーラー、ブルックナー他の新しくステージに上がる機会が多くなった作曲家の作品に比べ、ヘンデルは求めて聴きにいかないと生では聴けない作曲家になりつつあると感じる次第だ.生で聴くにしても、当時のような宮殿の広間(Saal)や 小部屋(Raum)又は教会内で、楽器編成も当時の様式で聴くことは、日本では略不可能となってしまったと感じる.バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、ハープシコードなどの弦楽器のみで演奏されるバッハ、ヘンデル時代の作品は、その端正な形式とテンポ良い曲想の運び、和声的な響きで近年に聞いても何とも聴き心地の良い音楽であると思う. しかし、クラシック音楽を好きになれない多くの人が、ヘンデルなどの音楽を聞くと直ぐに、退屈に感じ面白くないと思うらしいが、私にはその理由を説明出来ない.残念ながら、どうしようもない致し方ないとしか言いようがない. ヘンデルで先ず思い出すのはオラトリオ「メサイア」と「合奏協奏曲」だ. ※①「メサイア(救世主)」は、サー・エードリアン・ボールト指揮のロンドン交響楽団、同合唱団のLondonレコード盤で何度も聴いてきたが、今回、十数年振りに改めて聴き直すと矢張り良い.兎も角、和声とリズム、テンポが今の喧騒の世の中では貴重な精神的静寂の世界に連れ戻してくれる感じがする.特に、ジョーン・サザーランド(ソプラノ)の伸びのある高音の歌唱力には改めてその美しさに驚かされる.演奏はハープシコード、オルガンの音の上に、乾いたトランペットの音色が清々しく響き、歌手と合唱との調和が何とも美しく響く.長編のオラトリオ「救世主」の最後を飾る終末合唱(シュルス・コール)は、あらゆる点から、最も感動的な合唱で、規模も壮大で、まるでミケランジェロの壁画に生命を吹き込んだような名曲と思う. 他に、ザルツブルグのモーツアルト劇場でロバート・ウイルソン演出の公演(2020年1月)ビデオを鑑賞した.メサイアの演技を伴っての合唱、歌唱と管弦楽の形での舞台を観たのは初めてだが、セットや衣装は現代の意匠から遠く離れたSF的な無機質なものであった.音楽だけを聴いて空想の世界で音をイメージするのと、舞台上の具象化された人物などを観ながら音楽を聴くのとは、全く脳裏に映るイメージが違ってくるので、宗教曲「メサイア」は合唱、歌唱、管弦楽だけでの演奏会又はレコードやCDで鑑賞するのが私は断然好ましいと思った. ※②「合奏協奏曲 作品6」:(演奏:イタリア合奏団)を改めて通して聴いた.「メサイア(救世主)」と並んでヘンデルの代表曲だと感じた.「合奏協奏曲 作品6」を約3時間聞き通すのは、生では無理でもCDやレコードで十分に楽しめる長さだ.ワイングラス片手に涼しいそよ風に当たりながら聴けたら申し分のない曲だろうと空想を広げた. ※③「王宮の花火の音楽」:久しぶりに聴く、管楽器群の響き、特に高音のトランペットとホルンの透き通るような響きは悠久の世界観に漲る贅沢感がある. ※④3つの二重協奏曲 第2番ヘ長調(6楽章)及び第3番ヘ長調(6楽章)(Concerti a due cori)::上記に同じ.今の時代に又、直ぐに聴きたくなる音楽. 今回の雑感記録に際して、改めて聴き直した作曲家の作品リストをご参考までに下記、表にした.
- 9/3/2022 盛夏8月の発表会
ピアノ教室恒例の発表会(サマー・コンサート)が、昨年の夏に続き今年も去る8月6日に(@宝塚文化創造館 - 旧宝塚音楽学校校舎)開かれました.小学校低学年までが中心のこのピアノ教室でサックスにピアノ伴奏を付けて頂くレッスンを続けて、既に4年ほどになります.今回は24人の生徒さんのピアノ演奏の後のBreak Timeに、サックスの私と声楽とバイオリンの女性の講師との大人3人がピアノの伴奏でそれぞれ曲を演奏して、コロナ禍でも1年振りの爽快感を味わいました. 私の演奏曲はスワニー(Suwanee)/ ガシュイン作曲でした. リハーサルにて 発表会(サマー・コンサート)
- 7/25/2022 フィルム・レビュー「クローダッドが歌う場所」Where The Crawdads Sing
ミステリー/スリラー PG-13 スター:デイジー・エドガー・ジョーンズ、テイラー・ジョン・スミス、ハリス・ディキンソン、デヴィッド・ストラザーン 監督:オリビア・ニューマン 作家:ディーリア・オーウェンズ(彼女の小説に基づく)ルーシー・アリバル(脚本) 本あるいは映画?映画を観てから映画化された本を読むか、あるいは本を読んだ後で映画をみるか、どちらが良かったか自問しなければならないことがよくある.本と映画はそれぞれ独自の長所と短所を持つ異なる媒体であるため判断は大変に難しい. 受賞歴のある本書を3年ほど前に読んで、実際に視覚化できるストーリーがたくさんあったので、恐らく素晴らしい映画になるだろうと思った.その後、ハリウッドがこの小説を映画化していると聞いたとき、一日千秋の思いで映画化を待った.数日前にこの映画を見たが失望はしなかった.この映画は本に忠実だと思う.大きな違いのひとつは、一般的に言えることだが、本はキャラクターの背景や経験の一部に深く入り込んで書かれており、これは映画には見られない本独特の点で、映画の欠点であると思う.本を読んでいない人にとっては、キャストが下す決定があまりに突然で、混乱しているように見えるかもしれない.しかし、この映画はノース・カロライナの沼地の美しいシーンを映画でなければできないほど提供しており、それが大変に魅力的だと思う. 映画を見た後、私はプロが書いたこの映画のレビューをいくつか読んだ.そして私はそれらのいくつかがどれほど「否定的」であったのに驚いた.レビューをした人達は実際に本を読んだのか疑問に思った.概して彼らが同意したと思われる一点は、映画の中心である若い「マーシュ・ガール」であるキャラを演じるデイジー・エドガージョーンズの力強いパフォーマンスである.エドガー・ジョーンズはイギリス人女優で、その功績は恥ずかしがり屋で教育を受けていない南部の女の子を非常にリアルに描写している点である. 「Rotten Tomatoes」*では、映画評論家が映画に35を与えたのに、映画を見に行った映画ファンが96を与えた.これは大きな違いである!!!! 映画のプロモーションが少なかったので、私の推測だが、映画を見に行った人達は本も読んだ人達だったのではないかと思う.本あるいは映画?あなたが決めてほしい. クローダッドが歌う場所の公式予告編 https://www.youtube.com/watch?v=PY3808Iq0Tg https://youshofanclub.com/2019/04/24/crawdads-sing/ *全米の様々な作家協会・映画評論家団体が承認した執筆者による各映画のレビューが掲載され、スタッフが作品ごとに肯定・否定のそれぞれのレビューを集計.賛否の平均値は点数として掲出される (wiki).
- 7/10/2022 フィルム・レビュー 「エルビス Elvis」
ミュージカル/ドラマ PG-13 スター:オースティン・バトラー、トム・ハンクス、オリビア・デジョン 監督:バズ・ラーマン 作家:バズ・ラーマン、サム・ブロメル、クレイグ・ピアース エルビスの少年時代から1950年代にエルビスが「ロックの伝説」に至るまでの期間を紹介した伝記的にも正確なこの映画は、バズ・ラーマンの傑作である.映画の大部分は、若いミシシッピー出身の少年がどのようにして世界的に有名なスターになったのかを描いており、彼がマネージャーのトム・パーカー大佐(トム・ハンクスとはスクリーン上では認識できないがハンクスがパーカー大佐を演じている)との複雑な関係も示している. オースティン・バトラーは、エルビスを演じるカリスマ的な青年で、この映画を通してほぼ始めから終わりまで常にスクリーンに出ている魅力的な役者である.オースティン・バトラーは映画の中で「ロックンロールの王」をあたかも目撃していることを数時間信じさせるような外見、動き、そして声を持ってこの役を熱演している.またバトラーは映画のなかの歌を殆どすべて自分自身で歌っていることは注目に値すると思う. トム・パーカーがエルビスのマネージャーであり、スターを作った人物であることは知っていたが、パーカーは私にとっては不思議な存在であり、彼の風貌も覚えていない.あまり映画のストーリーの詳細をここで述べてしまうと観る楽しみが半減するのでやめにするが、この映画が教えてくれた一つの事実は、トム・パーカー大佐は大佐ではなく、トム・パーカーでもなかったということだ.彼はオランダのAndreas Cornelis Dries van Kuljkで生まれた! バズ・ラーマンは私の好きな映画監督の一人である.彼のスタイルは独特だと思う.オープニングにでるタイトルをみただけで、LuhrmannとわかるほどLuhrmann映画は紛れもない外観を持っている.照明、音楽、セット、衣装デザインの芸術をブレンドする彼のスキルは、他の映画監督とは異なる.ほんの数例を挙げると、オーストラリア、ムーラン・ルージュ、グレート・ギャツビーなどの彼の他の作品を読者のみなさんは見たことがあるかもしれない. 映画「エルビス」は、プリシラ・プレスリーとプレスリー一家全員から、「エルビスとエルビスの成功に貢献した人々の正直な描写である」と承認されたストーリーである.最大の映画スクリーンを備えつけた劇場に行ってこの映画を観ることを勧める. HBO/Maxでは約3ヶ月で公開されると聞いている. どちらが本物?
- 7/2/2022 本のレビュー、村上春樹著 女のいない男たち (Men Without Women)
この作品は映画「ドライブ・マイ・カー 英題:Drive My Car」で有名になった作品で、映画は「女のいない男たち」という村上春樹著の短編集の3作品で構成されているため、ブック・クラブでもその三作品を読んだ. <あらすじ> 1.「ドライブ・マイ・カー Drive My Car」 主人公家福は俳優で、妻は女優だったが10年以上前に死亡している.緑内障をきっかけに家福は若い女性運転手、みゆき、を薦められ雇うことにする.みゆきは家福の黄色のSaab 900コンバーティブルを無口で淡々と運転する.ある日、みゆきが家福に「友達は作らないの」と聞いたところ、家福は妻の浮気相手の高槻という男と偶然出会って「木野」というバーで飲み、その後も飲み友達のごとく何度もバーで会っては話したという.家福は「その高槻という男の言葉が心に響いたから、それ以来、友人はいない」と答えた. 2.「シェエラザード Scheherazade」 会社員男性と逢瀬を重ねる主婦は、男から「シェエラザード」という千夜一夜物語からのニックネームで呼ばれるようになる.女は逢う度に男に「女子高生が同級生の家に空き巣に入る」といった空想の話を聞かせる. 3.「木野 Kino」 木野という男の主人公は妻が同僚と浮気をしていたのを知ったのをきっかけに、会社を退職し、離婚し、その後ジャズ・バーを開く.やがて、妻が謝りに来て、野良猫が彼のバーに来るようになる.秋になると、まずその猫がいなくなり、それから蛇たちが姿を見せ始める. 〈ブック・クラブでの感想〉 ・映画のストーリーの中心になった「ドライブ・マイ・カー」では、妻の度重なる浮気を問いたださないまま、妻が亡くなってからも、現実から逃避する主人公が「自分は俳優だから、妻の浮気が頭をよぎった時には別の人物を演じる」と何度も語る箇所に興味をもった.俳優だから、というより、主人公は妻の浮気に寛容になれず「妻の人生と自分の人生は違うものだと考えられなかったのではないか?」また主人公は男のプライドが邪魔をして「正面から現実に向き合えないのではないか?」と思った. ・「シェエラザード」で会社員男性が会う主婦についての描写はひどすぎると思った.中年女性がどれだけ魅力がないかを延々と書いているのは、村上自身が女性を「物」として見ているからだと思う.彼の作品では、女性が登場した時の描写が安っぽい恋愛小説かと思う説明が多く、常に心にひっかかる. ・「木野」は本書の中でも、村上春樹ならではの異次元に連れていかれる感じを強く受けた.蛇がずっと頭をよぎるけれど、それが何の象徴なのか、結論がでないまま読み終えてしまった. ・「木野」はストーリーの展開が予想外だった.ブック・クラブ メンバーの「村上春樹が女性をどのようにとらえているか」についての鋭い意見と感想には目から鱗だった.今まで自分はそのようには考えてもみなかった. ・村上春樹は好きな作家ではなく、やはり今回の作品の感想も(ブック・クラブで以前読んだオーウェル、モーリヤック、ジョイス、イシグロの様に)読者に ”人生の味わい” や ”人生に関する何か” に気付く機会を与えたりするような作品ではなかった.つまり、本の内容が記憶に残らないと予測でき、やはりノーベル賞受賞作家のレベルとは違うような気がした(村上自身も恐らくノーベル賞を狙ってはいないと思うけれど).そして、出版が比較的最近であるにもかかわらず、女性の描写が古臭くバブル時代に書かれたのではないかと思った一節もあり、それでも彼の本が売れるのには少々驚く.但しサリン事件の「アンダー・グラウンド」は確かに力作だと思う.実際私も2000年頃のSaabに乗っていたが、故障が多くて長く乗れる車ではなく、特に日本で黄色のSaab 900コンバーティブルを乗っているということ自体が「この主人公はどのくらい目立ちたがり屋なんだ?」との考えがよぎる.今回の作品は、村上原作の著書より映画の方がよくできていたと思う.
.png)